1位

2025年10月28日
フリーワード検索

2022年05月25日生活・子育て
子どもが急に熱を出したり、けがをしたりするのは、よくあることです。
年齢や発達段階にもよりますが、子どもにとって自分の症状を大人に伝えることは難しいので、気づいたら症状が悪化していたということもあります。
大人が子どもの体調不良を予想するのは難しく、急な症状に慌てることも珍しくありません。
子どもの体調不良やけがで迷うのが「すぐに病院に行くかどうか」です。
特に働きながら子育てをしている方にとっては、仕事の調整もあるので、悩ましい瞬間だと思います。
そこで今回は、子どもに多い症状やけがを挙げたうえで、病院を受診する目安や普段から準備しておくといいことについて解説します。
ぜひ、仕事と育児の両立にお役立て下さい。
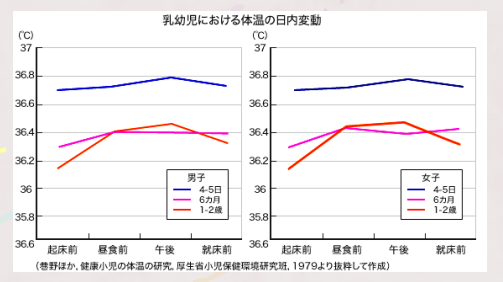
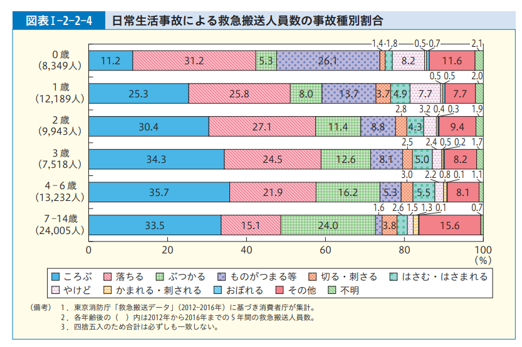
| (1) | 食事量、水分量、ミルクの量 |
| 栄養や水分が普段と比べて少なくないか、チェックします。 | |
| (2) | 排泄物の色、状態 |
| 例えば、子どもに多いロタウイルスは、便の色が白くなるという特徴があります。 便の色や状態は、病気を見分けるひとつの指針になります。 | |
| (3) | 嘔吐物の色、状態 |
| 排泄物と同様、嘔吐物の色や状態も重要な観察ポイントです。 嘔吐物に血が混ざっているときは消化管からの出血、緑色のときは胆汁が混ざっている可能性があります。 | |
| (4) | 睡眠がとれているか |
| 体調不良やけがで何らかの症状がある場合、睡眠時間が短くなったり睡眠が浅くなりがちです。 そうすると、体力が十分に回復せず、治るまでに時間がかかってしまいます。 | |
| (5) | 普段の様子と比べてどうか |
| 子どもの状態を観察するときの重要なポイントが、普段の様子と比べて変わったことがないかです。 これは、一緒に過ごしている大人にしか分かりません。 例えば、好きな遊びに誘っても興味を示さない、いつもよりもおしゃべりが少ないなど「あれ、おかしいな?」と思うときは注意が必要です。 |
| (1) | 無理に食べさせたり飲ませたりしない |
| 特に嘔吐や下痢が続くと脱水が心配になりますが、飲食によって状態が悪化した消化管にさらに負担をかけることになります。 栄養のバランスは一旦考えずに、食べやすいものを食べられる量、無理せず与えましょう。 水分も、少しずつ摂るようにします。 | |
| (2) | できるだけ家で安静にする |
| 子どもに「安静にして」と言っても難しいかもしれませんが、早くよくなるためにもある程度安静にすることは必要です。 カードゲームやブロックで遊ぶ、テレビや動画を見るなど、あまり体を動かさなくても楽しめる遊びを提案してみてください。 |
| (1) | 普段の様子と違って元気がない |
| 子どもが元気がないときには、何らかの原因があることが多いものです。 症状やけがの様子から問題なさそうと判断せず、すぐに病院に行きましょう。 反対に、熱や咳などの症状があっても、普段と変わらず過ごせているのであれば、慌てずに少し様子を見ても問題ない場合もあります。 | |
| (2) | 食事と水分が摂れず、尿の量が減った |
| 食事や水分が摂れず、尿の量が減ると、脱水の可能性が高くなります。 必要に応じて点滴を行い、栄養や水分量のバランスを調整する必要があります。 | |
| (3) | 嘔吐や下痢を何度も繰り返す |
| 嘔吐や下痢があっても、数回で治まり、その後元気に過ごせているのであれば問題ないことが多いでしょう。 しかし、何度も繰り返す場合は、詳しく検査をして適切な治療をしなければいけません。 | |
| (4) | 息苦しい |
| 息苦しさは体の中の酸素が足りなくなる可能性があり、また症状そのものによって不安が大きくなります。 呼吸の回数が多い、肩を使って呼吸をしている、顔や唇の色が悪いような場合には、すぐに病院を受診しましょう。 |
| (1) | 「普段と違う」と感じたことをメモしておく |
| 明確に症状が出ていなくても、「普段と違うな」と感じたことをメモしておくと、その後、何かの症状が出たときにいつから体調が悪くなったのか分かりやすくなります。 日にちと時間も忘れずに書いておきましょう。 | |
| (2) | 病院に必要な持ち物をまとめておく |
| 病院を受診する前は、大人も慌てがちです。 そんなときに、診察券や保険証、お薬手帳など、必要なものをすぐに持っていけるようにまとめておくと便利です。 また、普段子どもと過ごしている人ではない人が病院に連れていくこともあると思います。 そのときのために、家族みんなで置き場所を把握しておきましょう。 | |
| (3) | 信頼できるかかりつけ医を見つけておく |
| かかりつけ医を決めておくと、普段の子どもの様子が分かっているので、診察の精度が上がります。 そのため、あちこちの病院を受診せず、できるだけかかりつけ医を決めるようにしましょう。 もし他の病院を受診するときは、これまでの経過や処方された薬を伝えます。 | |
| (4) | 夜間や休日に診てくれる診療所を調べておく |
| 各自治体には、夜間や休日に診察してくれる診療所があります。 自宅の近くの診療所はどこにあるのか、電話番号や診療時間を事前に調べておくと、いざというときに慌てません。 また、夜間や休日に病院を受診するか迷ったときの連絡先として「子ども医療電話相談事業」があります。*3 全国どこからでも、「#8000」に電話をすると、医師や看護師が必要な対応をアドバイスしてくれます。 病院に行くかどうかの相談にも応じてもらえるので、不安がある場合は相談しましょう。 |

1位

2025年10月28日
2位

2024年08月02日
3位

2025年12月09日
2025年12月23日

2025年12月09日

2025年10月28日